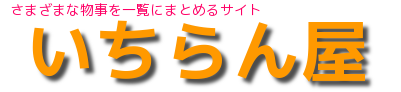最近更新したページ
▲先頭へ▲
最近更新したページ
地震の単位の種類一覧
サイト名とURLをコピーする
地震の単位の種類一覧の概要
地震とは岩盤が断層に沿って急激にずれ動く事で、地面に大きな振動が生じる事で、
発生方法や状態により様々な地震に分類(詳細:地震の種類一覧)されます。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 震度 |
地震の揺れの大きさを表す単位です。 地震の強さではなく、揺れの大きさを表すため、震源地から遠くても地盤の弱いとことや水を含む場所での震度は大きい値となります。 震度には階級の種類が複数あり、日本では「気象庁震度階級」が使用されています。 |
| 気象庁震度階級 |
日本で使用されている震度で、気象庁などが中心となり1884年に定められ、1996年に修正が行われました。 現在は全国約4200台の地震計を設置し、震度の情報を取得しています。 気象庁震度階級は以下の階級に分かれています。
|
| メルカリ震度階級 |
ロッシ・フォレル震度階級を元に、イタリアの火山学者ジュゼッペ・メルカリによって考案された震度階級です。 メルカリ震度階級は数度にわたり修正され、「メルカリ・カンニーニ・シーベルグ震度階級」 「メルカリ・ウッド・ニューマン震度階級」「改正メルカリ震度階級」などの震度階級が作られました。 メルカリ震度階級は以下の階級に分かれています。
|
| メドヴェーデフ・シュポンホイアー・カルニク震度階級 |
「MSK震度階級」とも呼ばれている震度階級で、1964年に作られロシアや東欧諸国、イスラエル、インドなどで使われています。 メドヴェーデフ・シュポンホイアー・カルニク震度階級は以下の階級に分かれています。
|
|
|
|
| 地震烈度 |
「中国地震震度」「中国地震烈度」等とも呼ばれている、中華人民共和国(中国)で使用されている12段階の震度階級です。 地震烈度は地震による体感や実際の被害状況と、地震波の加速度などを組み合わせて算出されています。 |
| ロッシ・フォレル震度階級 | ロッシ・フォレル震度階級は以前にヨーロッパなどで使用されていた10段階の震度階級です。 |
| ヨーロッパ震度階級 |
ヨーロッパ地震協会により1988年に作られた震度階級で1998年に修正されています。 ヨーロッパ震度階級は12段階に分かれた階級で、ヨーロッパ各国で使用されています。 |
| マグニチュード |
天文学や地震学で規模や大きさを表す単位として使用され、地震学では地震が起こすエネルギーの大きさを表す単位として利用されています。 地震のマグニチュードは2増えると1000倍になり、地球上で起こる最大の地震は「マグニチュード10」と考えられており、 記録に残る過去最大の地震のマグニチュードはM9.5の1960年チリ地震となっています。 また、マグニチュードにもいくつかの種類があります。 |
| モーメントマグニチュード | 断層の面積・変位・断層の地殻の剛性から算出するマグニチュードで、大規模な地震でも適切な値を算出しやすい特徴があり、現在多く使用されているマグニチュードです。 |
| リヒターマグニチュード | アメリカの地震学者チャールズ・リヒターにより定義されたマグニチュードで、震源から100km離れた場所で地震計が記録した揺れ幅を表します。 |
| 表面波マグニチュード | 主に大地震などの際に使用される単位で、大地震で発生する表面波の最大深度から算出するマグニチュードです。 |
| 実体波マグニチュード | マグニチュードの算出方法に、地震による揺れの波の周期、震源までの距離と深さを加味して算出されるマグニチュードです。 |
| 気象庁マグニチュード |
日本の気象庁で使用されているマグニチュードで記号はMjで表されます。 気象庁マグニチュードは2003年9月25日に1度改定されており、それ以前と以降では算出方法が変わるため、同じ地震でも資料などによりマグニチュードが違うことがあります。 |
| ガル |
記号:Gal 加速度の単位で、地震の振動加速度を求める際に利用されることがあります。 また、ガルはガリレオ・ガリレイに因んで付けられた単位であるため「ガリレオ(galileo)」と表記する場合も有ります。 |
| カイン |
記号:kain 地震による振動の大きさを速度の単位で表す記号です。 1カイン = 1cm毎秒 となっています。 |
関連ページ
▲先頭へ▲