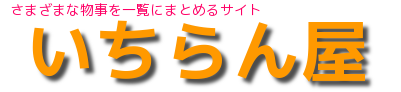最近更新したページ
▲先頭へ▲
最近更新したページ
日本の古代豪族の一覧
サイト名とURLをコピーする
2017年5月28日 壬生吉志氏を追加
日本の古代豪族の一覧の概要
豪族とは地方地域において強力な権力や軍事力を持ち、その地域を支配していた有力な氏族を指します。
豪族にはヤマト政権成立までの地方地域を支配していた勢力や首長層などを指す古代豪族や、武家社会においては地方の有力武士団や権力を持つ豪農などが豪族とも呼ばれることがありました。
このページでは主に古代豪族と呼ばれるヤマト政権成立前後の豪族をまとめています。この時代は古墳時代とも呼ばれるように多くの大規模古墳を作ったほか、氏神として自分達が崇拝する神様や祖先を祭る神社なども作り、後にそれぞれの豪族がヤマト政権に取り込まれる際に一体化され現在の神道の中に取り込まれました。
古代豪族には初期から天皇家に強力をした機内地域の中央系豪族、地方の豪族でヤマト政権に強力した地方系豪族、中国大陸や朝鮮半島から移住した民族の渡来系豪族に分類されます。
また、嵯峨天皇により編纂された古代氏族の名鑑である『新撰姓氏録』では、神武天皇以降に天皇家から分かれた氏族の『皇別』、神武天皇以前の時代に天皇家から分かれた氏族や天孫降臨の際にニニギノミコトと共に地上に降臨した神々の子孫である『神別』、渡来人などの子孫である『諸蕃』、上記3つに含まれない『その他の氏族』に分類されています。
豪族にはヤマト政権成立までの地方地域を支配していた勢力や首長層などを指す古代豪族や、武家社会においては地方の有力武士団や権力を持つ豪農などが豪族とも呼ばれることがありました。
このページでは主に古代豪族と呼ばれるヤマト政権成立前後の豪族をまとめています。この時代は古墳時代とも呼ばれるように多くの大規模古墳を作ったほか、氏神として自分達が崇拝する神様や祖先を祭る神社なども作り、後にそれぞれの豪族がヤマト政権に取り込まれる際に一体化され現在の神道の中に取り込まれました。
古代豪族には初期から天皇家に強力をした機内地域の中央系豪族、地方の豪族でヤマト政権に強力した地方系豪族、中国大陸や朝鮮半島から移住した民族の渡来系豪族に分類されます。
また、嵯峨天皇により編纂された古代氏族の名鑑である『新撰姓氏録』では、神武天皇以降に天皇家から分かれた氏族の『皇別』、神武天皇以前の時代に天皇家から分かれた氏族や天孫降臨の際にニニギノミコトと共に地上に降臨した神々の子孫である『神別』、渡来人などの子孫である『諸蕃』、上記3つに含まれない『その他の氏族』に分類されています。
日本の古代豪族の氏族一覧
他田氏
他田氏は科野国造であった科野氏の子孫の家系であるとされ、現在の長野県で力を持っていた豪族です。
長野県の諏訪湖周囲に位置する二社四宮の諏訪神社の神職である諏訪氏とも深い関係が有るとされ、長野県上田市にある下之郷古墳群の他田塚古墳はその名の通り他田氏の関係者が埋葬されたと伝えられています。
長野県の諏訪湖周囲に位置する二社四宮の諏訪神社の神職である諏訪氏とも深い関係が有るとされ、長野県上田市にある下之郷古墳群の他田塚古墳はその名の通り他田氏の関係者が埋葬されたと伝えられています。
阿蘇氏
阿蘇氏は現在の熊本県に位置した阿蘇国北東部付近を支配していた豪族で、阿蘇国造でもありました。
健磐龍命の子である速瓶玉命を祖としており、熊本県阿蘇市には速瓶玉命を祭神として祭った国造神社も残されています。
阿蘇氏は古くから阿蘇山の神への司祭的立場であった一族が力を持ち豪族になったと考えられており、健磐龍命などを祭神とした阿蘇神社の大宮司を代々務めています。
健磐龍命の子である速瓶玉命を祖としており、熊本県阿蘇市には速瓶玉命を祭神として祭った国造神社も残されています。
阿蘇氏は古くから阿蘇山の神への司祭的立場であった一族が力を持ち豪族になったと考えられており、健磐龍命などを祭神とした阿蘇神社の大宮司を代々務めています。
阿多氏
阿多氏は現在の鹿児島県西部に位置した薩摩国を支配していた豪族で、薩摩国造でもありました。
阿部氏
阿部氏は孝元天皇の皇子である大彦命を祖とする豪族で、大和国十市郡阿倍を本拠地としていました。
飛鳥時代から奈良時代にかけては阿倍内麻呂や阿倍比羅夫などの高官や将軍などを輩出した有力な氏族で、平安時代頃に安倍氏に改めて安倍晴明などを輩出し以降は陰陽師の家系となりました。
飛鳥時代から奈良時代にかけては阿倍内麻呂や阿倍比羅夫などの高官や将軍などを輩出した有力な氏族で、平安時代頃に安倍氏に改めて安倍晴明などを輩出し以降は陰陽師の家系となりました。
阿保氏
阿保氏は息速別命を祖とする系統と、於知別命を祖とする系統があります。
息速別命を祖とする系統は三重県西部の伊賀市や名張市に位置した伊賀国を支配していた豪族で伊賀国造でもありました。
息速別命の子孫である須珍都斗王から阿保姓を賜りました。
於知別命を祖とする系統には現在の滋賀県草津市や栗東市などの地域を支配していた豪族である小槻山君などがおり、子孫の今雄・有緒・良眞らが阿保姓を賜りました。
息速別命を祖とする系統は三重県西部の伊賀市や名張市に位置した伊賀国を支配していた豪族で伊賀国造でもありました。
息速別命の子孫である須珍都斗王から阿保姓を賜りました。
於知別命を祖とする系統には現在の滋賀県草津市や栗東市などの地域を支配していた豪族である小槻山君などがおり、子孫の今雄・有緒・良眞らが阿保姓を賜りました。
阿牟氏
阿牟氏は現在の山口県萩市や阿武郡などを支配していた豪族で、阿武国造でもありました。
神魂命の子孫であり味波波命を祖としています。
神魂命の子孫であり味波波命を祖としています。
葦北氏(日奉氏)
葦北氏は現在の熊本県に位置した肥後国南部の地域を支配していた豪族で、葦北国造でもありました。
吉備津彦命の子である三井根子命を祖としており、後に日奉の姓を賜りました。
吉備津彦命の子である三井根子命を祖としており、後に日奉の姓を賜りました。
粟氏
粟氏は徳島県に位置した阿波国の北部を支配していた豪族で、粟国造(阿波国造)でもありました。
高皇産霊尊の子孫である千波足尼を祖としており、徳島県名西郡石井町の中王子神社には神体として祭られていた阿波国造墓碑があります。
徳島県鳴門市には萩原墳墓群、天河別神社古墳群、宝幢寺古墳群など大規模な古墳が多く残り、粟国造であった粟氏に関連した人物の墓であったと考えられています。
高皇産霊尊の子孫である千波足尼を祖としており、徳島県名西郡石井町の中王子神社には神体として祭られていた阿波国造墓碑があります。
徳島県鳴門市には萩原墳墓群、天河別神社古墳群、宝幢寺古墳群など大規模な古墳が多く残り、粟国造であった粟氏に関連した人物の墓であったと考えられています。
安氏
安氏は現在の滋賀県に位置した近江国の東部を支配していた豪族で、安国造(淡海安国造、近淡海安国造)でもありました。
彦坐王の子である水穂真若王の子孫の系統で、円山古墳、甲山古墳、古冨波山などを含む大岩山古墳群は安氏に関連する人物の墓とされています。
彦坐王の子である水穂真若王の子孫の系統で、円山古墳、甲山古墳、古冨波山などを含む大岩山古墳群は安氏に関連する人物の墓とされています。
安曇氏(阿曇氏)
安曇氏(阿曇氏)は現在の福岡県に位置した備前国糟屋郡に本拠地を持っていた豪族で、海人族と呼ばれる古くから中国大陸や朝鮮半島などとの海洋交易などで力を付けた一族です。
海の神である綿津見神の子孫であるとされ、後に本拠地であった九州から全国各地に移住し愛知県の渥美半島や、長野県の安曇野などの地名は安曇氏に由来があるとされています。
海の神である綿津見神の子孫であるとされ、後に本拠地であった九州から全国各地に移住し愛知県の渥美半島や、長野県の安曇野などの地名は安曇氏に由来があるとされています。
庵原氏(廬原氏)
庵原氏(廬原氏)は現在の静岡県に位置した駿河国の西部を支配していた豪族で、廬原国造でもありました。
吉備建彦の子である意加部彦を祖としており、多くの勢力を誇っていたとされ、白村江の戦いでは軍を率いて戦いました。
また、後の世では今川氏の傘下として桶狭間の戦いにも参戦しています。
吉備建彦の子である意加部彦を祖としており、多くの勢力を誇っていたとされ、白村江の戦いでは軍を率いて戦いました。
また、後の世では今川氏の傘下として桶狭間の戦いにも参戦しています。
伊勢氏
伊勢氏は現在の三重県・愛知県・岐阜県にまたがる伊勢国を支配していた豪族で、伊勢国造でもありました。
天日鷲命または天日鷲命を祖としています。なお、天日鷲命と天日鷲命は別人説と同一人物説があります。
天日鷲命または天日鷲命を祖としています。なお、天日鷲命と天日鷲命は別人説と同一人物説があります。
伊豆氏
伊豆氏は現在の静岡県伊豆半島に位置した伊豆国を支配していた豪族で、伊豆国造でもありました。
天蕤桙命の子孫である若建命を祖としています。
天蕤桙命の子孫である若建命を祖としています。
伊余氏
伊余氏は現在の愛媛県伊予市や伊予郡に位置した、伊予国南部を支配していた豪族で、伊余国造でもありました。
敷桁彦命の子である速後上命を祖としています。
敷桁彦命の子である速後上命を祖としています。
磯城氏
磯城氏は現在の奈良県桜井市付近を本拠地としていたとされる豪族です。
古事記と日本書紀に登場する最古の豪族の1つで、欠史八代と呼ばれる第2代綏靖天皇から第9代開化天皇までの皇后の多くが磯城氏に関連した女性となっております。
しかし、欠史八代の天皇は存在していたという証拠が乏しく、磯城氏についても存在が不明でなぞの多い豪族となっております。
古事記と日本書紀に登場する最古の豪族の1つで、欠史八代と呼ばれる第2代綏靖天皇から第9代開化天皇までの皇后の多くが磯城氏に関連した女性となっております。
しかし、欠史八代の天皇は存在していたという証拠が乏しく、磯城氏についても存在が不明でなぞの多い豪族となっております。
壱岐氏
壱岐氏(伊岐氏・伊吉氏・壱伎氏)は現在の長崎県壱岐市(壱岐島)に有った壱岐国を支配していた豪族で、壱岐国造(伊吉島造)でも有りました。
壱岐氏には中臣烏賊津の子孫である氏族と、大陸から渡ってきた渡来人の子孫の氏族がいるとされています。
壱岐氏には中臣烏賊津の子孫である氏族と、大陸から渡ってきた渡来人の子孫の氏族がいるとされています。
因幡氏
因幡氏は鳥取県東部に位置した因幡国を支配していた豪族で、因幡国造(稲葉国造)でもありました。
彦坐王の子である彦多都彦命を祖としており、大和政権の勢力が因幡に及ぶよりも古い時代からこの地を支配していたと考えられています。
因幡国一宮である宇倍神社の神主の家系である伊福部氏は因幡氏から別れた氏族でも有ります。
彦坐王の子である彦多都彦命を祖としており、大和政権の勢力が因幡に及ぶよりも古い時代からこの地を支配していたと考えられています。
因幡国一宮である宇倍神社の神主の家系である伊福部氏は因幡氏から別れた氏族でも有ります。
宇佐氏
宇佐氏は現在の大分県に位置した豊前国宇佐郡付近を支配していた豪族で、宇佐都彦命(菟狭津彦)を祖としています。
宇佐国造を世襲したとの説のありますが、真意は不明のようです。
宇佐氏は宇佐神宮(宇佐八幡宮)の大宮司を代々務めており、鎌倉時代末期に宇佐氏は宮成家と到津家に別れ、宇佐神宮の神職を交互に担っています。
宇佐国造を世襲したとの説のありますが、真意は不明のようです。
宇佐氏は宇佐神宮(宇佐八幡宮)の大宮司を代々務めており、鎌倉時代末期に宇佐氏は宮成家と到津家に別れ、宇佐神宮の神職を交互に担っています。
越氏
越氏は現在の新潟県中部地方を支配していた豪族で、高志国造でもあります。
屋主田心命の子孫である市入命を始祖としています。
屋主田心命の子孫である市入命を始祖としています。
越智氏(伊予国)
伊予国の越智氏は現在の愛媛県今治市付近にあった伊予国越智郷を本拠地とした豪族で、孝霊天皇の子孫である越智王が始祖であると考えられています。
越智氏 (大和国)
大和国の越智氏は現在の奈良県に位置した大和国高市郡越智荘を支配していた豪族です。
始祖は不明ですが、物部氏と関連のある氏族説や、伊予国の河野氏の末裔説、源頼親の子孫などの説が有ります。
始祖は不明ですが、物部氏と関連のある氏族説や、伊予国の河野氏の末裔説、源頼親の子孫などの説が有ります。
大神氏
大神氏は豊後国大野郡や直入郡を中心に、豊後国の南部を支配していた豪族で、三輪氏系統の大和国の大神氏と区別するため、豊後大神氏とも表記されます。
大神惟基を祖としており、大和国の大神氏と繋がりがあるとも言われています。
大神惟基を祖としており、大和国の大神氏と繋がりがあるとも言われています。
下道氏
下道氏は現在の岡山県倉敷市や総社市付近を支配した豪族で、下道国造でもありました。
御友別の子である兄彦命(稲速別命)を祖としており、吉備氏の一族にあたる氏族とされています。
下道氏の支配していた岡山県小田郡矢掛町には国指定重要文化財の「下道公の墓」と呼ばれる遺跡もあります。
御友別の子である兄彦命(稲速別命)を祖としており、吉備氏の一族にあたる氏族とされています。
下道氏の支配していた岡山県小田郡矢掛町には国指定重要文化財の「下道公の墓」と呼ばれる遺跡もあります。
科野氏
科野氏は現在の長野県に位置する信濃国を支配していた豪族で、科野国造でもありました。
崇神天皇の子孫である建五百建命を祖としており、後に科野氏から金刺氏や他田氏に分かれたとされています。
科野国の位置した地域には森将軍塚古墳を含む埴科古墳群、川柳将軍塚古墳、倉科将軍塚古墳など大規模な古墳が発見されており、いくつかの古墳は科野氏に関係があると伝えられています。
崇神天皇の子孫である建五百建命を祖としており、後に科野氏から金刺氏や他田氏に分かれたとされています。
科野国の位置した地域には森将軍塚古墳を含む埴科古墳群、川柳将軍塚古墳、倉科将軍塚古墳など大規模な古墳が発見されており、いくつかの古墳は科野氏に関係があると伝えられています。
賀茂氏
賀茂氏は現在の京都府南部に位置した山城国の葛野郡や愛宕郡を支配していた豪族で、上賀茂神社(賀茂別雷神社)と下鴨神社(賀茂御祖神社)の祠官を務めていました。
また賀茂氏には複数の氏族が折り、代表的な賀茂氏には現在の奈良県御所市付近に位置する大和国葛上郡鴨周辺を支配していた三輪氏の系統の豪族である賀茂氏も存在します。
また賀茂氏には複数の氏族が折り、代表的な賀茂氏には現在の奈良県御所市付近に位置する大和国葛上郡鴨周辺を支配していた三輪氏の系統の豪族である賀茂氏も存在します。
角氏
角氏は現在の山口県周南市都濃付近を支配していた豪族で、都怒国造でもありました。
都怒足尼の子である田鳥足尼を祖としています。
都怒足尼の子である田鳥足尼を祖としています。
角鹿氏
角鹿氏は現在の福井県に位置した越前国旧敦賀郡を支配していた豪族で、角鹿国造でもありました。
孝霊天皇の子孫である建功狭日命を祖としており、現在も角鹿氏の一族である島家(角鹿氏の苗字は島)の分家が角鹿国造家を継承しています。
敦賀市にある中郷古墳群(明神山古墳群、向出山古墳群)は、角鹿氏に関連したものであると考えられています。
孝霊天皇の子孫である建功狭日命を祖としており、現在も角鹿氏の一族である島家(角鹿氏の苗字は島)の分家が角鹿国造家を継承しています。
敦賀市にある中郷古墳群(明神山古墳群、向出山古墳群)は、角鹿氏に関連したものであると考えられています。
笠氏
笠氏は現在の岡山県西部に位置した備中国の南東部を支配していた豪族で、笠臣国造でもありました。
古くからこの地域を支配していたようで、鴨別命の子孫である笠三枚臣が応神天皇により国造に定められた事が笠氏の始まりとされています。
古くからこの地域を支配していたようで、鴨別命の子孫である笠三枚臣が応神天皇により国造に定められた事が笠氏の始まりとされています。
葛城氏
葛城氏は現在の奈良県葛城市付近の大和葛城に本拠地を置いていた豪族で、武内宿禰の子である葛城襲津彦を祖としている氏族です。
古くから有力な豪族であるとされ、天皇家とも婚姻関係を持っています。
また、もう一方の葛城氏として剣根命を祖とする系統があり、葛城地方の神社の奉斎などを執り行っていたとされています。
古くから有力な豪族であるとされ、天皇家とも婚姻関係を持っています。
また、もう一方の葛城氏として剣根命を祖とする系統があり、葛城地方の神社の奉斎などを執り行っていたとされています。
岩城氏(磐城氏)
岩城氏(磐城氏)は現在の茨城県に位置した常陸国の東部を支配していた豪族で、高国造でもありました。
天穂日命の子である建比良鳥命を祖としています。
天穂日命の子である建比良鳥命を祖としています。
忌部氏
忌部氏は現在の奈良県橿原市忌部町付近に位置した大和国高市郡忌部を本拠地とした豪族で、古くから朝廷の祭事を執り行うほか、祭具の作成や宮殿の造園などを執り行っていました。
天太玉命を祖としており803年には氏名を斎部氏に改めました。
天太玉命を祖としており803年には氏名を斎部氏に改めました。
紀氏
紀氏は現在の奈良県に位置した大和国平群県紀里付近を支配していた豪族で、武内宿禰の子である紀角を始祖としています。
朝鮮半島への出兵や蝦夷の反乱の鎮圧など軍事力を持っていたほか、大納言や中納言の官職、歌人や文人など多くの有能な人物を輩出しています。
朝鮮半島への出兵や蝦夷の反乱の鎮圧など軍事力を持っていたほか、大納言や中納言の官職、歌人や文人など多くの有能な人物を輩出しています。
吉備氏
吉備氏は現在の岡山県に位置した吉備国を支配していた豪族で、孝霊天皇の子で稚武彦命の子孫であるとされています。
古くから強力な力を持った豪族であったとされ、岡山県岡山市にある造山古墳や岡山県総社市にある作山古墳など、吉備氏の支配した地域には大規模な古墳などが多く残されています
古くから強力な力を持った豪族であったとされ、岡山県岡山市にある造山古墳や岡山県総社市にある作山古墳など、吉備氏の支配した地域には大規模な古墳などが多く残されています
橘氏
橘氏は県犬養氏出身の女官である県犬養三千代が、天皇から「橘宿禰」の氏姓を受け出来た氏族で、県犬養三千代とその子である橘諸兄と橘佐為を祖としています。
現在の多くの氏姓に繋がるとされる「源平藤橘」に数えられる有力な豪族で、平安時代中期まで多くの公家を輩出しました。
現在の多くの氏姓に繋がるとされる「源平藤橘」に数えられる有力な豪族で、平安時代中期まで多くの公家を輩出しました。
久努氏
久努氏は現在の静岡県西部に位置した遠江国東部を支配していた豪族で、久努国造でもありました。
伊香色男命の子孫である印播足尼を祖としています。
伊香色男命の子孫である印播足尼を祖としています。
久米氏
久米氏とは高御魂命の子孫の味耳命の後裔の氏と、神魂命の子孫である味日命後裔の氏があり、九州方面の出身であると考えられています。
久米氏は大伴氏と同等または配下に位置した氏族で、ある程度の軍事力を保持していたとされています。
久米氏は大伴氏と同等または配下に位置した氏族で、ある程度の軍事力を保持していたとされています。
巨勢氏
巨勢氏は大和国高市郡巨勢郷に本拠地を置いていた豪族で、許勢氏・許世氏・居勢氏・己西氏・既洒氏などの表記も見られます。
武内宿禰の次男である許勢小柄宿禰を祖としており、大臣や大夫などを輩出しました。
武内宿禰の次男である許勢小柄宿禰を祖としており、大臣や大夫などを輩出しました。
金刺氏
金刺氏は現在の静岡県東部を支配していた豪族で、珠流河国造(駿河国造)でもありました。
大新川命の子の片堅石命を祖としており、欽明天皇の皇居であった磯城嶋金刺宮の管理などを行っていた氏族だとされています。
大新川命の子の片堅石命を祖としており、欽明天皇の皇居であった磯城嶋金刺宮の管理などを行っていた氏族だとされています。
熊野氏
熊野氏は現在の和歌山県と三重県に位置した熊野国を支配していた豪族で、熊野国造でもありました。
饒速日命の子孫である大阿刀足尼を祖としています。
熊野氏は代々熊野本宮大社の禰宜の職についており、後に和田氏を名乗りました。
饒速日命の子孫である大阿刀足尼を祖としています。
熊野氏は代々熊野本宮大社の禰宜の職についており、後に和田氏を名乗りました。
穴門氏
穴門氏は現在の山口県西部に位置した長門国の西部を支配していた豪族で、穴門国造でもありました。
邇伎都美命の子孫である速都鳥命を祖としています。
邇伎都美命の子孫である速都鳥命を祖としています。
県犬養氏
県犬養氏は神魂命の子孫とされる氏族で、朝廷の直轄領などの守衛などの職を担っていました。
県犬養氏の一族で女官であった県犬養三千代は元明天皇から橘の氏を受け賜り、橘氏の始祖となりました。
県犬養氏の一族で女官であった県犬養三千代は元明天皇から橘の氏を受け賜り、橘氏の始祖となりました。
江沼氏
江沼氏は現在の石川県南部に位置した加賀国の南部地域を支配していた豪族で、江沼国造でもありました。
武内宿禰の子孫である志波勝足尼を祖としており、加賀市東部の江沼平野に位置する南郷古墳群・吸坂古墳群・黒瀬古墳群の埋葬者は江沼氏の一族であると考えられています。
武内宿禰の子孫である志波勝足尼を祖としており、加賀市東部の江沼平野に位置する南郷古墳群・吸坂古墳群・黒瀬古墳群の埋葬者は江沼氏の一族であると考えられています。
香夜氏(賀陽氏)
香夜氏(賀陽氏)は現在の岡山県西部に位置した地域を支配していた豪族で、加夜国造でもありました。
香夜氏はかつてよりこの地を支配していた中彦命を国造に定めたことで始まった氏族です。
香夜氏はかつてよりこの地を支配していた中彦命を国造に定めたことで始まった氏族です。
国前氏
国前氏は大分県に位置した豊後国の北部地域を支配していた豪族で、国前国造でもありました。
吉備都命の子孫である午佐自命を祖としています。
吉備都命の子孫である午佐自命を祖としています。
佐伯氏
佐伯氏は大伴室屋の代に大伴氏から別れたとされる氏族で、東日本で捕虜となった現地人を率いて宮廷の警備や兵として朝廷に仕えていました。
佐伯氏には針間国造であった針間氏が氏を改めて佐伯氏となった系統や、現在の広島県西部を支配していた豪族の佐伯氏もおり、こちらは安芸国造(阿岐国造)であり、厳島神社の神主を代々務めていました。
佐伯氏には針間国造であった針間氏が氏を改めて佐伯氏となった系統や、現在の広島県西部を支配していた豪族の佐伯氏もおり、こちらは安芸国造(阿岐国造)であり、厳島神社の神主を代々務めていました。
三使部氏
三使部氏は現在の岡山県に位置した備中国東部を支配していた豪族で、吉備中県国造でもありました。
神祝命の子孫である明石彦を祖としております。
神祝命の子孫である明石彦を祖としております。
三野後氏(美濃後氏)
三野後氏(美濃後氏)は現在の岐阜県南部地域を支配していた豪族で、三野後国造でもありました。
出雲大臣命の孫の臣賀夫良命を祖としており、岐阜市にある金神社境内には臣賀夫良命の墓とされる賀夫良命塚があります。
三野後国造は後に三野前国造に吸収されたと考えられています。
出雲大臣命の孫の臣賀夫良命を祖としており、岐阜市にある金神社境内には臣賀夫良命の墓とされる賀夫良命塚があります。
三野後国造は後に三野前国造に吸収されたと考えられています。
三野氏(美濃氏)
三野氏(美濃氏)は現在の岐阜県中西部を支配していた豪族で、三野前国造でもありました。
開化天皇の孫とされる神大根王を祖としており、岐阜県本巣市にある宗慶大塚古墳は神大根王の墓であるとされています。
開化天皇の孫とされる神大根王を祖としており、岐阜県本巣市にある宗慶大塚古墳は神大根王の墓であるとされています。
三野本巣氏
三野本巣氏は現在の岐阜県中西部を支配していた豪族で、本巣国造でもありました。
開化天皇の孫とされる神大根王を祖としており、後に三野全域を統一したと考えられています。
開化天皇の孫とされる神大根王を祖としており、後に三野全域を統一したと考えられています。
三輪氏
三輪氏は現在の奈良県に位置した大和国磯城地方の豪族で、大神氏や大三輪氏とも表記されます。
大和国城上郡大神郷の地名が氏の由来となったようで、大神神社を氏神としています。
大物主神の子である大田田根子を祖としています。
大和国城上郡大神郷の地名が氏の由来となったようで、大神神社を氏神としています。
大物主神の子である大田田根子を祖としています。
山背氏
山背氏(山代氏)は現在の京都府南部にあった山背国西部を支配していた豪族で、山背国造(山代国造)でもありました。
讃岐氏
讃岐氏は現在の香川県に位置した讃岐国を支配していた豪族で、讃岐国造でもありました。
神櫛皇子の子孫の須賣保禮命を祖としています。
神櫛皇子の子孫の須賣保禮命を祖としています。
漆部氏
漆部氏は現在の神奈川県東部に位置した相武国を支配していた豪族で、相武国造でもありました。
弟武彦命を祖としており、寒川神社が氏神となっています。
弟武彦命を祖としており、寒川神社が氏神となっています。
射水氏
射水氏は現在の富山県に位置した越中国にあった伊彌頭国を支配していた豪族で、伊彌頭国造でもありました。
武内宿禰の孫である大河音足尼を祖としており、富山県高岡市にある桜谷古墳は大河音足尼の子孫か射水氏一族の墓であると考えられています。
武内宿禰の孫である大河音足尼を祖としており、富山県高岡市にある桜谷古墳は大河音足尼の子孫か射水氏一族の墓であると考えられています。
周防氏
周防氏は現在の山口県に位置した周防国の東部を支配した豪族で、周防国造でもありました。
加米乃意美を祖としており、山口県柳井市にある柳井茶臼山古墳は周防氏のものと見られています。
加米乃意美を祖としており、山口県柳井市にある柳井茶臼山古墳は周防氏のものと見られています。
十市氏
十市氏は大和国に本拠地を置いていた豪族で、現在の奈良県橿原市十市町辺りに居住地があったと思われています。
奈良県橿原市にある十市御縣坐神社が氏神であると考えられていますが、十市氏については不明な点が多くなぞに包まれている氏族でもあります。
奈良県橿原市にある十市御縣坐神社が氏神であると考えられていますが、十市氏については不明な点が多くなぞに包まれている氏族でもあります。
出雲氏
出雲氏は現在の島根県東部地方にあった出雲国を支配していた豪族で、出雲国造でもあり出雲大社の祭祀を執り行っています。
天穂日命を初代とする家系で、1340年頃には千家氏と北島氏に分かれ、千家氏は出雲大社教、北島氏は出雲教とそれぞれ宗教法人を作り、双方が出雲国造を名乗っています。
天穂日命を初代とする家系で、1340年頃には千家氏と北島氏に分かれ、千家氏は出雲大社教、北島氏は出雲教とそれぞれ宗教法人を作り、双方が出雲国造を名乗っています。
春日氏
春日氏は孝昭天皇の皇子である天足彦国押人命を祖とする和珥氏の一部が、大和国添上郡の春日に移住したことで春日氏を名乗りました。
小市氏
小市氏は現在の愛媛県にあった伊予国の東部の地域を支配していた豪族で、小市国造でもありました。
大新川命の孫の子致命の家系で、物部大小市連を祖としています。
小市氏は後に越智郡に移住して越智氏を名乗るようになりました。
愛媛県今治市にある鯨山古墳は越智氏の墓であるとされています。
大新川命の孫の子致命の家系で、物部大小市連を祖としています。
小市氏は後に越智郡に移住して越智氏を名乗るようになりました。
愛媛県今治市にある鯨山古墳は越智氏の墓であるとされています。
上道氏
上道氏は現在の岡山県や兵庫県の一部に位置した備前国の南東部を支配していた豪族で、上道国造でもありました。
中彦命の子である多佐臣を祖としており、岡山県赤磐市にある両宮山古墳群は上道氏のものと見られています。
中彦命の子である多佐臣を祖としており、岡山県赤磐市にある両宮山古墳群は上道氏のものと見られています。
上毛野氏
上毛野氏は現在の群馬県に位置した上野国を支配していた豪族で上毛野国造でもありました。
上毛野国造としては崇神天皇の皇子である豊城入彦命を祖としており、上毛野氏は蝦夷討伐や百済救済の軍の将軍職などを担当しました。
また上毛野氏は古くから大陸との交流も有ったようで、渡来人系の流れを汲む部族もいました。
なお上毛野氏は後述の下毛野氏と共に古くからこの地域を支配ていたヤマト王権に匹敵するほどの強大な豪族で、現在の群馬県を中心に1万基以上の古墳などが作られました。
氏神として赤城山をご神体とする赤城神社を祭っています。
上毛野国造としては崇神天皇の皇子である豊城入彦命を祖としており、上毛野氏は蝦夷討伐や百済救済の軍の将軍職などを担当しました。
また上毛野氏は古くから大陸との交流も有ったようで、渡来人系の流れを汲む部族もいました。
なお上毛野氏は後述の下毛野氏と共に古くからこの地域を支配ていたヤマト王権に匹敵するほどの強大な豪族で、現在の群馬県を中心に1万基以上の古墳などが作られました。
氏神として赤城山をご神体とする赤城神社を祭っています。
下毛野氏
下毛野氏は現在の栃木県南部地域を支配していた豪族で、下毛野国造でもありました。
元々は上記の上毛野氏と同じ毛野氏であったとされていますが、分割されそれぞれ上野国と下野国を支配するようになりました。
崇神天皇の子である豊城入彦命の子孫の奈良別を祖としています。なお、豊城入彦命は下毛野国の隣に位置した上毛野国(現在の群馬県)を支配した上毛野氏の祖でもあります。
下毛野国には摩利支天塚古墳、琵琶塚古墳、吾妻古墳などの大規模な前方後円墳のほか、下野型古墳と呼ばれる独自の形状をした前方後円墳が多く見られ、これらの古墳が下毛野氏のものだと考えられています。
氏神には日光二荒山神社や宇都宮二荒山神社などがあります。
元々は上記の上毛野氏と同じ毛野氏であったとされていますが、分割されそれぞれ上野国と下野国を支配するようになりました。
崇神天皇の子である豊城入彦命の子孫の奈良別を祖としています。なお、豊城入彦命は下毛野国の隣に位置した上毛野国(現在の群馬県)を支配した上毛野氏の祖でもあります。
下毛野国には摩利支天塚古墳、琵琶塚古墳、吾妻古墳などの大規模な前方後円墳のほか、下野型古墳と呼ばれる独自の形状をした前方後円墳が多く見られ、これらの古墳が下毛野氏のものだと考えられています。
氏神には日光二荒山神社や宇都宮二荒山神社などがあります。
丈部氏
丈部氏は現在の千葉県成田氏・佐倉市・八街市・四街道市・印西市などの地域にあたる印波国を支配していた豪族で、印波国造でもありました。
神八井耳命の子孫の伊都許利命を祖としており、麻賀多神社が氏神となっています。
千葉県成田市にある公津ヶ原古墳群や龍角寺古墳群の大規模古墳は丈部氏または同じく印波国造であった生部氏に関連があるとされています。
神八井耳命の子孫の伊都許利命を祖としており、麻賀多神社が氏神となっています。
千葉県成田市にある公津ヶ原古墳群や龍角寺古墳群の大規模古墳は丈部氏または同じく印波国造であった生部氏に関連があるとされています。
新治氏
新治氏は現在の茨城県に位置した常陸国の西部を支配した豪族で、新治国造でもありました。
比奈良珠命(比奈良珠命、比奈布命)を祖としており、新治氏に関連する遺跡には葦間山古墳や新治郡衙跡などがあります。
比奈良珠命(比奈良珠命、比奈布命)を祖としており、新治氏に関連する遺跡には葦間山古墳や新治郡衙跡などがあります。
秦氏
秦氏は渡来系の民族による氏族で、百済系、辰韓系、新羅系、後秦系、前秦系、秦王国系など様々な説がります。
当初は豊前国などに拠点を置いていましたが、中央政権に進出するとともに各地に広がっていき、神奈川県の秦野市は秦氏が入植したことからこの名が付いたとされています。
渡来系であることから土木、養蚕、漆器、などの大陸の技術に明るく、淀川の工事や桂川に葛野大堰などの治水工事を行いました。
当初は豊前国などに拠点を置いていましたが、中央政権に進出するとともに各地に広がっていき、神奈川県の秦野市は秦氏が入植したことからこの名が付いたとされています。
渡来系であることから土木、養蚕、漆器、などの大陸の技術に明るく、淀川の工事や桂川に葛野大堰などの治水工事を行いました。
針間氏
針間氏は現在の兵庫県南西部に位置した播磨国北部を支配していた豪族で、播磨国造でもありました。
景行天皇の皇子である稲背入彦皇子の系統の氏族です。
本来は佐伯氏でありましたが、播磨国造を任命された際に針間氏に改めました。後に針間別佐伯直となりましたが、戸籍である庚午年籍作成の際に佐伯直となりました。
景行天皇の皇子である稲背入彦皇子の系統の氏族です。
本来は佐伯氏でありましたが、播磨国造を任命された際に針間氏に改めました。後に針間別佐伯直となりましたが、戸籍である庚午年籍作成の際に佐伯直となりました。
壬生氏
壬生氏は現在の茨城県に位置する常陸国の大部分を支配していた豪族で、茨城国造でもありました。
天津彦根命の子孫である筑紫刀禰を祖としております。
天津彦根命の子孫である筑紫刀禰を祖としております。
石城氏
石城氏は現在の福島県浜通りのいわき市から大熊町付近に位置した石城国を支配していた豪族で、石城国造でもありました。
天津彦根命の子である建許呂命を祖としており、大國魂神社が氏神となっています。
また、国の史跡である甲塚古墳は、建許侶命を葬ったと伝えられています。
天津彦根命の子である建許呂命を祖としており、大國魂神社が氏神となっています。
また、国の史跡である甲塚古墳は、建許侶命を葬ったと伝えられています。
膳氏
膳氏は現在の福井県南部付近を支配していた豪族で、若狭国造でもありました。
膳氏は孝元天皇皇子の子孫である磐鹿六雁命を祖としていおり、朝廷や皇室の料理を担当する役職にあったとされています。
膳氏は後に高橋氏へと氏を改めました。
膳氏は孝元天皇皇子の子孫である磐鹿六雁命を祖としていおり、朝廷や皇室の料理を担当する役職にあったとされています。
膳氏は後に高橋氏へと氏を改めました。
曾禰氏
曾禰氏は饒速日命の子孫である伊香色雄命の系統とされている氏族です。
一族の有名な人には、小倉百人一首で46番の歌をうたった曽禰好忠などがいます。
一族の有名な人には、小倉百人一首で46番の歌をうたった曽禰好忠などがいます。
蘇我氏
蘇我氏は現在の奈良県に位置する大和国高市郡蘇我邑を本拠地としていた豪族で、武内宿禰を祖としています。
渡来系の一族と関係が深く、日本への仏教の伝来も担いました。
一族の女子を天皇家に嫁がせるなどして天皇家との関係も深いほか、多くの大臣を輩出した一大豪族でのありました。
蘇我氏一族の有名な人物には、蘇我稲目、蘇我馬子、蘇我蝦夷、蘇我入鹿などがいます。
渡来系の一族と関係が深く、日本への仏教の伝来も担いました。
一族の女子を天皇家に嫁がせるなどして天皇家との関係も深いほか、多くの大臣を輩出した一大豪族でのありました。
蘇我氏一族の有名な人物には、蘇我稲目、蘇我馬子、蘇我蝦夷、蘇我入鹿などがいます。
息長氏
息長氏は現在の滋賀県米原市付近に位置した近江国坂田郡に本拠地を持っていた豪族です。
応神天皇の子である意富富杼王を祖としており、息長古墳群は息長氏一族のものであると考えられています。
応神天皇の子である意富富杼王を祖としており、息長古墳群は息長氏一族のものであると考えられています。
他田日奉部氏
他田日奉部氏は現在の千葉県旭市や銚子市などを支配していた豪族で、下海上国造(下菟上国造)でもありました。
関東平野東部に存在していた香取海の交通や交易などを支配していたと考えられています。
久都伎直を祖としており、香取神宮が氏神となっています。
関東平野東部に存在していた香取海の交通や交易などを支配していたと考えられています。
久都伎直を祖としており、香取神宮が氏神となっています。
多氏
多氏は九州に本拠地を置いていた豪族で、神武天皇の子である神八井耳命の子孫らの氏族とされています。
多氏の一部は現在の奈良県に位置する大和国に移り住み、その地を本拠地としました。
多氏からは多くの有力豪族や氏族が子孫として残されており、伊余國造、石城国造、科野国造、道奧石城國造、常道仲國造、長狹國造などの国造にもなっています。
多氏の一部は現在の奈良県に位置する大和国に移り住み、その地を本拠地としました。
多氏からは多くの有力豪族や氏族が子孫として残されており、伊余國造、石城国造、科野国造、道奧石城國造、常道仲國造、長狹國造などの国造にもなっています。
多治比氏
多治比氏は現在の大阪府東部に位置した河内国を支配していた豪族で、宣化天皇の子孫である多治比古王が祖となっています。
丹治比氏、丹墀氏、多治氏、丹治氏などと表記されることも有ります。
多治比氏の一族は右大臣、大納言、中納言などの高官を輩出しています。
丹治比氏、丹墀氏、多治氏、丹治氏などと表記されることも有ります。
多治比氏の一族は右大臣、大納言、中納言などの高官を輩出しています。
大隅氏
大隅氏は現在の鹿児島県東部や奄美群島に位置した大隅国を支配していた豪族で、大隅国造でもありました。
大荒木氏
大荒木氏は現在の新潟県の佐渡島を支配していた豪族で、佐渡国造でもありました。
久志伊麻命の子孫である大荒木直を祖としています。
久志伊麻命の子孫である大荒木直を祖としています。
大私部氏
大私部氏は現在の千葉県千葉市付近に位置した地域を支配していた豪族で、千葉国造(知波国造)でもありました。
大中臣氏
大中臣氏は現在の京都府にあった山城国に本拠地をもっていた氏族で、中臣氏の家系で有りましたが中臣意美麻呂とその子である清麻呂の功績が大きかったことからあった大の字を承り大中臣氏となりました。
大中臣氏は祭事や神事を司る神祇官や伊勢神宮の祭主などを平安時代ごろまで世襲していました。
大中臣氏は祭事や神事を司る神祇官や伊勢神宮の祭主などを平安時代ごろまで世襲していました。
大伴氏
大伴氏は古くから多くの朝廷の役人を束ねていたとされる一族で、摂津国や河内国などを本拠地としていました。
天忍日命の子孫である道臣命を始祖としており、多くの公卿などの高官や歌人などを輩出しており、大伴直大瀧は阿波国造(現在の千葉県南部に位置する安房国)にも任命されています。
後に淳和天皇(大伴親王)が即位すると忌み名を避ける為に伴氏へと氏名を改めました。
天忍日命の子孫である道臣命を始祖としており、多くの公卿などの高官や歌人などを輩出しており、大伴直大瀧は阿波国造(現在の千葉県南部に位置する安房国)にも任命されています。
後に淳和天皇(大伴親王)が即位すると忌み名を避ける為に伴氏へと氏名を改めました。
大分氏
大分氏は現在の大分県に位置した豊後国北部地域を支配していた豪族で、大分国造でもありました。
景行天皇の皇子である豊門別命が始祖とされており、大分氏一族の有名な人物には共に壬申の乱で大海人皇子の軍に参加し活躍した大分稚臣や大分恵尺などがります。
景行天皇の皇子である豊門別命が始祖とされており、大分氏一族の有名な人物には共に壬申の乱で大海人皇子の軍に参加し活躍した大分稚臣や大分恵尺などがります。
但馬氏
但馬氏は現在の兵庫県北部に位置する但馬国の東部を支配していた豪族で、但遅麻国造でもありました。
彦座王の子孫である船穂足尼を祖としています。
彦座王の子孫である船穂足尼を祖としています。
丹波氏
丹波氏は現在の京都府中部、兵庫県北部、大阪府の一部に位置した丹波国(令制国の丹波国、但馬国、丹後国にあたる地域)を支配していた豪族で、丹波国造でもあります。
建稲種命の子孫である大倉岐命を祖としています。
建稲種命の子孫である大倉岐命を祖としています。
淡道氏
淡道氏は現在の兵庫県淡路島にあった淡路国を支配していた豪族で、淡路国造でもありました。
神皇産霊尊の子孫である矢口足尼を祖としています。
神皇産霊尊の子孫である矢口足尼を祖としています。
筑紫氏
筑紫氏は現在の福岡県に位置する筑紫国(筑前国と筑後国の範囲)を支配していた豪族で、筑紫国造でもありました。
大彦命の子孫である田道命を祖としています。
大彦命の子孫である田道命を祖としています。
筑紫米多氏
筑紫米多氏は現在の佐賀県や長崎県に位置した肥前国の東部地域を支配していた豪族で、筑志米多国造(竺志米多国造)でもありました。
応神天皇の子孫である都紀女加を祖としています。
応神天皇の子孫である都紀女加を祖としています。
中臣氏
中臣氏は現在の京都府山科区の中臣町付近を本拠地としていた豪族で、古くから神事や祭祀に係わっていました。
天児屋命を祖としており、一族内で有名な人物には中臣鎌足などがいます。
天児屋命を祖としており、一族内で有名な人物には中臣鎌足などがいます。
長氏
長氏は現在の徳島県南部に有った地域を支配していた豪族で、長国造でもありました。
観松彦伊呂止命の子孫である韓背足尼を祖としています。
観松彦伊呂止命の子孫である韓背足尼を祖としています。
津島県氏
津島県氏は現在の長崎県の対馬を支配していた豪族で、津嶋国造でもありました。
初代津嶋国造となった高皇産霊神の子孫である建彌己己命が祖となっています。
初代津嶋国造となった高皇産霊神の子孫である建彌己己命が祖となっています。
土師氏
土師氏は大阪府藤井寺市付近を本拠地としていた豪族で、古墳の作成や葬送の儀礼などに関わった氏族とされています。
天穂日命の子孫である野見宿禰を祖としており、垂仁天皇の皇后である日葉酢媛命が亡くなった際に、野見宿禰が殉死の代わりに埴輪を作成し生きた人のかわりに埋めることを提案し喜んだ垂仁天皇から土師の姓を授かりました。
天穂日命の子孫である野見宿禰を祖としており、垂仁天皇の皇后である日葉酢媛命が亡くなった際に、野見宿禰が殉死の代わりに埴輪を作成し生きた人のかわりに埋めることを提案し喜んだ垂仁天皇から土師の姓を授かりました。
島氏
島氏は、現在の三重県志摩地方にあった志摩国を支配していた豪族で、志摩国造でもありました。
天穂日命の子孫である出雲笠夜命を祖としています。
天穂日命の子孫である出雲笠夜命を祖としています。
漢氏
漢氏は漢の渡来人である阿知使主を祖とする大陸からの帰化氏族です。
東漢氏
東漢氏は漢の渡来人である阿知使主を祖とする大陸からの帰化氏族で、様々な帰化人集団が東漢氏を名乗ったと考えられています。
大和国の飛鳥地方に拠点を構えていたとされ、大陸からの製鉄技術などにより軍事力を持ち、武器の開発や宮廷の警護などを行っていました。
大和国の飛鳥地方に拠点を構えていたとされ、大陸からの製鉄技術などにより軍事力を持ち、武器の開発や宮廷の警護などを行っていました。
西漢氏
西漢氏は百済から日本に渡来した「王仁」を祖とする氏族です。
道氏
道氏は現在の石川県南部にあった加賀国を統治していた豪族で、加賀国造でもありました。
初代加賀国造であった素都乃奈美留命を祖としています。
初代加賀国造であった素都乃奈美留命を祖としています。
那須氏
那須氏は現在の栃木県に位置した下野国那須郡を統治していた豪族で、那須国造でもあります。
藤原道長の後裔である藤原資家を祖としており、須藤氏を称した後に那須氏となりました。
那須氏一族の有名人として那須与一などがいます。
藤原道長の後裔である藤原資家を祖としており、須藤氏を称した後に那須氏となりました。
那須氏一族の有名人として那須与一などがいます。
日下部氏
日下部氏は、但馬国造であった日下部君の系統または、孝徳天皇の孫であった日下部宿禰(表米宿禰)の系統とされる豪族です。
日下部氏は日本の各地にいたとされなぞの多い氏族ですが、後にいくつかの武家家系が日下部氏の末裔であるとしているため、各地に配置された軍事集団であったと見られています。
日下部氏は日本の各地にいたとされなぞの多い氏族ですが、後にいくつかの武家家系が日下部氏の末裔であるとしているため、各地に配置された軍事集団であったと見られています。
能登氏
能登氏は現在の石川県北部の能登半島付近に位置した能登国を支配していた豪族で、能登国造でもありました。
初代能登国造で有った孝霊天皇の子である彦狭島命を祖としています。
初代能登国造で有った孝霊天皇の子である彦狭島命を祖としています。
波多氏
波多氏にはいくつかの系統があります。
武内宿禰裔の末裔の波多氏は、武内宿禰の長男である波多八代宿禰を祖としており、大和国高市郡波多郷を本拠地としていた豪族です。
意富富杼王の末裔の波多氏は、応神天皇の孫である意富富杼王を祖としており、大和国高市郡波多郷に由来があると考えられています。
この波多氏は後に羽田氏に改められました。
波多国造の波多氏は、現在の高知県西部を支配しており波多国造でもありました。
この波多氏は天韓襲命を祖としています。
そのほかの波多氏として、日本武尊の末裔の系統、百済国からの渡来人であった佐布利智使主の子孫の系統、坂上志拏の三男である阿良を祖とする系統が有ります。
武内宿禰裔の末裔の波多氏は、武内宿禰の長男である波多八代宿禰を祖としており、大和国高市郡波多郷を本拠地としていた豪族です。
意富富杼王の末裔の波多氏は、応神天皇の孫である意富富杼王を祖としており、大和国高市郡波多郷に由来があると考えられています。
この波多氏は後に羽田氏に改められました。
波多国造の波多氏は、現在の高知県西部を支配しており波多国造でもありました。
この波多氏は天韓襲命を祖としています。
そのほかの波多氏として、日本武尊の末裔の系統、百済国からの渡来人であった佐布利智使主の子孫の系統、坂上志拏の三男である阿良を祖とする系統が有ります。
伯岐氏(伯耆氏)
伯岐氏(伯耆氏)は現在の鳥取県中部と西部に位置した伯耆国を統治していた豪族で、伯岐国造(波伯国造)でもありました。
兄多毛比命の子である大八木足尼が初代の伯岐国造と任命されたことから大八木足尼を祖としています。
兄多毛比命の子である大八木足尼が初代の伯岐国造と任命されたことから大八木足尼を祖としています。
斐陀氏
斐陀氏は現在の岐阜県北部に存在した飛騨国を統治していた豪族で、斐陀国造でもありました。
瀛津世襲命の子のである大八埼命を祖としています。
瀛津世襲命の子のである大八埼命を祖としています。
肥氏
肥氏は肥前国(佐賀県と長崎県)と肥後国(熊本県)にわたる火国(肥国)を統治していた豪族で、火国造でもありました。
神武天皇の皇子である神八井耳命または、その子供である健磐龍命を祖としています。
神武天皇の皇子である神八井耳命または、その子供である健磐龍命を祖としています。
尾張氏
尾張氏は現在の愛知県に有った尾張国を統治していた豪族で、尾張国造(尾治国造)でも有りました。
天火明命を祖としており、天皇家との結びつきが有るなど、ヤマト王権の中でも大きな権力を誇っていました。
また、平安時代後期まで熱田神宮の大宮司、平安時代後期以降は権宮司を代々務めています。
天火明命を祖としており、天皇家との結びつきが有るなど、ヤマト王権の中でも大きな権力を誇っていました。
また、平安時代後期まで熱田神宮の大宮司、平安時代後期以降は権宮司を代々務めています。
百済王氏
百済王氏は朝鮮半島に存在した国家である「百済」の最後の王である義慈王の子供「禅広王(善光王)」を祖とする氏族です。
百済国は当時の倭国と同名を組んでおり、百済国の王子である「豊璋王」「禅広王(善光王)」を人質として倭国に送っていました。
なお、豊璋王は唐により滅ぼされた百済国復興のために朝鮮半島に戻りましたが、白村江の戦いで破れ唐にとらえられました。
百済王氏は陸奥国や出羽国など東北地方の統治や、蝦夷の討伐などの要職を担っていました。
百済王氏からは常陸国の税務長官などを担った百済氏などの氏族も輩出しています。
百済国は当時の倭国と同名を組んでおり、百済国の王子である「豊璋王」「禅広王(善光王)」を人質として倭国に送っていました。
なお、豊璋王は唐により滅ぼされた百済国復興のために朝鮮半島に戻りましたが、白村江の戦いで破れ唐にとらえられました。
百済王氏は陸奥国や出羽国など東北地方の統治や、蝦夷の討伐などの要職を担っていました。
百済王氏からは常陸国の税務長官などを担った百済氏などの氏族も輩出しています。
品治氏
品治氏は現在の広島県東部に位置した備後国の南部を統治していた豪族で、吉備品治国造(吉備風治国造)でもありました。
若角城命の子孫である大船足尼が吉備品治国造に任命されたことで、品治氏の祖となっています。
若角城命の子孫である大船足尼が吉備品治国造に任命されたことで、品治氏の祖となっています。
風早氏
風早氏は現在の愛媛県中部に位置した風早郡を統治していた豪族で、風早国造でもありました。
伊香色男命の子孫である阿佐利命が初代風早国造となり、風早氏の祖となっています。
伊香色男命の子孫である阿佐利命が初代風早国造となり、風早氏の祖となっています。
物部氏
物部氏は現在の奈良県や大阪府に位置した大和国山辺郡や河内国渋川郡を支配していた有力な軍事豪族で、「磐井の乱」の鎮圧などを行っています。
饒速日命の子孫である「物部十千根」を祖としており、西暦686年の朱鳥元年頃には本家筋が物部氏から石上氏に改めています。
饒速日命の子孫である「物部十千根」を祖としており、西暦686年の朱鳥元年頃には本家筋が物部氏から石上氏に改めています。
平群氏
平群氏は現在の奈良県生駒郡付近にあった大和国平群郡などを支配していた豪族です。
武内宿禰の第4子である「平群木菟」を祖としています。
武内宿禰の第4子である「平群木菟」を祖としています。
穂積氏
穂積氏は現在の奈良県に位置する大和国山辺郡や十市郡などを支配していた豪族で、饒速日命(ニギハヤヒ)の末裔である穂積真津を祖としています。
穂積氏の一族には百済に派遣された穂積押山、征新羅副将軍に任命された穂積祖足などがおり、穂積氏から分かれた氏族には采女氏や藤白鈴木氏などがあります。
穂積氏の一族には百済に派遣された穂積押山、征新羅副将軍に任命された穂積祖足などがおり、穂積氏から分かれた氏族には采女氏や藤白鈴木氏などがあります。
豊氏
豊氏は現在の大分県と福岡県東部に位置した豊国を支配していた豪族で、豊国造でもありました。
天穂日命の子孫である宇那足尼を祖としています。
天穂日命の子孫である宇那足尼を祖としています。
凡河内氏
凡河内氏は現在の大阪府や兵庫県に位置した、河内国・摂津国・和泉国を支配していた豪族で、凡河内国造(凡川内国造・大河内国造)でもありました。
天津彦根命の末裔、天穂日命の末裔、後漢孝献帝の血筋を引いたの渡来人の3系統の祖があると考えられています。
天津彦根命の末裔、天穂日命の末裔、後漢孝献帝の血筋を引いたの渡来人の3系統の祖があると考えられています。
末氏
末氏は現在の千葉県小糸川流域にあった須恵国を支配していた豪族で、須恵国造(周淮国造)でもありました。
天津彦根命の子孫である建許呂命の子「大布日意彌命」を祖としており、千葉県富津市にある内裏塚古墳群は末氏関係者の物と考えられています。
天津彦根命の子孫である建許呂命の子「大布日意彌命」を祖としており、千葉県富津市にある内裏塚古墳群は末氏関係者の物と考えられています。
牟義都氏
牟義都氏は現在の岐阜県南部にあった美濃国北中部を支配していた豪族で、牟義都国造でもありました。
なお、牟義都国造は牟宜都国造や身毛津国造などと表記する事も有ります。
牟義都氏の祖は景行天皇の子である大碓命と神大根王の娘の弟比売の間に出来た「押黒弟日子王」としており、牟義都氏の表記も「牟下都氏」「牟下津氏」「牟宜都氏」「牟宜津氏」など様々有ります。
なお、牟義都国造は牟宜都国造や身毛津国造などと表記する事も有ります。
牟義都氏の祖は景行天皇の子である大碓命と神大根王の娘の弟比売の間に出来た「押黒弟日子王」としており、牟義都氏の表記も「牟下都氏」「牟下津氏」「牟宜都氏」「牟宜津氏」など様々有ります。
牟邪氏
牟邪氏は現在の千葉県山武市付近にあった上総国武射郡地域を支配していた豪族で、武社国造でもありました。
書物「古事記」では孝昭天皇の皇子である天足彦国押人命が祖となっています。
書物「古事記」では孝昭天皇の皇子である天足彦国押人命が祖となっています。
倭氏
倭氏は現在の奈良県付近にあった大和国中部地域を支配していた豪族で、倭国造(大倭国造)でもありました。
神武天皇が大和を征服した「神武東征」の際に水先案内などを行い、倭国造に命じられたとされています。
奈良時代頃に国名が倭国から数回にわたり改名されると、それに伴い氏族名も大倭氏、大養徳氏、大和氏に変わりました。
神武天皇が大和を征服した「神武東征」の際に水先案内などを行い、倭国造に命じられたとされています。
奈良時代頃に国名が倭国から数回にわたり改名されると、それに伴い氏族名も大倭氏、大養徳氏、大和氏に変わりました。
和気氏
和気氏は現在の岡山県にあった備前国を支配していた豪族で、垂仁天皇の子供である「鐸石別命(ぬてしわけのみこと)」が祖となっているようです。
後に「和気真人」「和気宿禰」「和気朝臣」などの氏姓となりました。
後に「和気真人」「和気宿禰」「和気朝臣」などの氏姓となりました。
和邇氏(和珥氏)
和邇氏は現在の奈良県付近にあった大和国添上郡付近を本拠地とした豪族で、孝昭天皇の第一皇子である「天足彦国押人命」が祖となっているようです。
檜前氏
檜前氏は現在の千葉県市原氏付近にあった上総国海上郡を支配していた豪族で、上海上国造(上菟上国造)でもありました。
百済からの渡来人である阿知使主の末裔が檜前氏になったとされています。
百済からの渡来人である阿知使主の末裔が檜前氏になったとされています。
羽咋氏
羽咋氏は現在の石川県羽咋郡や羽咋市付近にあった羽咋国を支配していた豪族で、羽咋国造でもありました。
垂仁天皇の皇子である石衝別王を祖としています。
垂仁天皇の皇子である石衝別王を祖としています。
諸県氏(諸縣氏)
諸県氏は現在の宮崎県の位置する日向国を支配していた豪族で、日向国造でもありました。
景行天皇の末裔である「老男」を祖としているようで、老男の子供である「牛諸井」が諸県君を命じられたことで元となっています。
景行天皇の末裔である「老男」を祖としているようで、老男の子供である「牛諸井」が諸県君を命じられたことで元となっています。
都祁氏
都祁氏は現在の奈良県付近にあった大和国東部を支配していた豪族で、闘鶏国造(都祁国造、都下国造)でもありました。
神武天皇の皇子である神八井耳命を祖としているようです。
神武天皇の皇子である神八井耳命を祖としているようです。
都佐氏(土佐氏)
都佐氏は現在の高知県東部にあった都佐国を支配していた豪族で、都佐国造でもありました。
神武天皇の妻である「媛蹈鞴五十鈴媛命(ヒメタタライススヒメ)」の母である「玉櫛媛」の父親である「三島溝橛耳」の末裔の「小立足尼」を祖としています。
神武天皇の妻である「媛蹈鞴五十鈴媛命(ヒメタタライススヒメ)」の母である「玉櫛媛」の父親である「三島溝橛耳」の末裔の「小立足尼」を祖としています。
筑波氏
筑波氏は現在の茨城県つくば市周辺を支配していた豪族で、筑波国造でもありました。
忍凝見命の子孫である阿閉色命を祖としており、茨城県つくば市にある八幡塚古墳は初代筑波国造であった阿閉色命の墓だといわれています。
筑波氏は茨城県つくば市筑波にある筑波山神社を氏神としており、代々筑波氏が神職を担っていました。
忍凝見命の子孫である阿閉色命を祖としており、茨城県つくば市にある八幡塚古墳は初代筑波国造であった阿閉色命の墓だといわれています。
筑波氏は茨城県つくば市筑波にある筑波山神社を氏神としており、代々筑波氏が神職を担っていました。
釆女氏
釆女氏は穂積氏から分かれた氏族で、穂積真津の次男・采女宮手を祖としています。
主に天皇や皇后の身の回りの世話をする女官である「采女(うぬめ)」を統括していたとされています。
主に天皇や皇后の身の回りの世話をする女官である「采女(うぬめ)」を統括していたとされています。
淡海氏(近江氏)
淡海氏(近江氏)とは現在の滋賀県の琵琶湖西岸地域を支配していた豪族で、淡海国造(近江国造)でも有りました。
天足彦国押人命を祖としており、後に琵琶湖東岸地域を支配していた安国造(淡海安国造)を合併して滋賀県全域にわたる近江国を支配したとされています。
天足彦国押人命を祖としており、後に琵琶湖東岸地域を支配していた安国造(淡海安国造)を合併して滋賀県全域にわたる近江国を支配したとされています。
諏訪氏
諏訪氏は現在の長野県に位置する諏訪地方を支配していた豪族で、諏訪大社の上社の祭事を司っていました。また、建御名方神の子孫とされており、金刺氏などとも近い氏族であるとされています
藤原氏
藤原氏は、藤原鎌足を祖とする豪族で、源平藤橘(源氏・平氏・藤原氏・橘氏)で知られる名門氏族の1つでもありました。藤原鎌足が天智天皇から「藤原」の姓を賜ったことに始まり、天皇家などとも婚姻関係を持ち政治においても非常に強い力を持っていました。
奈良時代には「藤原南家」「藤原北家」「藤原式家」「藤原京家」の藤原四家に別れ、鎌倉時代には藤原北家から「近衛家」「鷹司家」「九条家」「二条家」「一条家」などの有力氏族へと分裂しました。
奈良時代には「藤原南家」「藤原北家」「藤原式家」「藤原京家」の藤原四家に別れ、鎌倉時代には藤原北家から「近衛家」「鷹司家」「九条家」「二条家」「一条家」などの有力氏族へと分裂しました。
武蔵氏
武蔵氏は現在の埼玉県南部や東京都の一部地域を支配していた豪族で、无邪志国造(武蔵国造、無邪志国造、牟邪志国造、无謝志国造)でもありました。
武蔵氏は出雲国造と同系統の氏族が現在の地に移住し大宮氷川神社を祭ったとされ、代々大宮氷川神社の祭事を執り行っていました。
武蔵氏は出雲国造と同系統の氏族が現在の地に移住し大宮氷川神社を祭ったとされ、代々大宮氷川神社の祭事を執り行っていました。
中原氏
中原氏は安寧天皇の第三皇子の磯城津彦命を祖としている豪族です。
大外記、少外記と呼ばれる職を世襲したほか、学問である明法道と明経道を司どっていました。
大外記、少外記と呼ばれる職を世襲したほか、学問である明法道と明経道を司どっていました。
宗像氏
宗像氏(胸形氏、宗形氏、胸肩氏とも記載される)は福岡県の宗像市・宮若市・古賀市の地域である宗像地方と、響灘西部や玄界灘全域を支配していた豪族です。
宗像氏は沖ノ島の沖津宮、筑前大島の中津宮、宗像市田島の辺津宮の三社をまとめた、宗像大社を氏神として祭り、宗像大社神主や大宮司を代々受け継いでいました。
宗像氏は沖ノ島の沖津宮、筑前大島の中津宮、宗像市田島の辺津宮の三社をまとめた、宗像大社を氏神として祭り、宗像大社神主や大宮司を代々受け継いでいました。
水沼氏(水間氏)
水沼氏(水間氏)は現在の筑紫地方を支配していたとされる豪族で、国乳別皇子を祖としています。
筑後国一宮である高良大社や、福岡県久留米市にある御塚・権現塚古墳とも関係があるとされています。
筑後国一宮である高良大社や、福岡県久留米市にある御塚・権現塚古墳とも関係があるとされています。
卜部氏
卜部氏は卜占と呼ばれる占いで朝廷の神事などで吉凶判断を行っていた氏族で、占部・浦部・浦邊などとも表記されます。
卜部氏には不明な点も多いようですが、五十手命を祖とする伊豆系統、天児屋根命12世の孫にあたる雷大臣の子の真根子を祖とする壱岐系統、対馬県直の一族で建弥己己命を祖とする対馬系統の流れがあります。
卜部氏には不明な点も多いようですが、五十手命を祖とする伊豆系統、天児屋根命12世の孫にあたる雷大臣の子の真根子を祖とする壱岐系統、対馬県直の一族で建弥己己命を祖とする対馬系統の流れがあります。
筑紫氏
筑紫氏は福岡県西部地域にあった筑紫国を支配していた豪族で、筑紫国造でもありました。
筑紫氏は渡来人との交流も深く、新羅に奪われた地域を奪還しに朝鮮に出兵をしようとしていたヤマト王権軍に、新羅に協力した筑紫君磐井が起こした反乱である「磐井の乱」でも知られています。
福岡県筑紫野市の筑紫神社にも関連があるとされています。
筑紫氏は渡来人との交流も深く、新羅に奪われた地域を奪還しに朝鮮に出兵をしようとしていたヤマト王権軍に、新羅に協力した筑紫君磐井が起こした反乱である「磐井の乱」でも知られています。
福岡県筑紫野市の筑紫神社にも関連があるとされています。
高麗氏
高麗氏は現在の埼玉県の日高市や鶴ヶ島市などを中心とした地域である、武蔵国高麗郡を支配していた豪族で、朝鮮半島にあった高句麗国の子孫の一族です。
高句麗は668年に唐に滅ぼされたため、高句麗の人達は日本に避難をしてきました。その人達が朝廷の命令で武蔵国に集められ、その地域が高麗郡と名づけられました。
高麗郡に済む人達のリーダーには高句麗の王族であった高麗王若光がおり、高麗王若光が亡くなると霊廟が建てられそれが高麗神社となりました。
高麗神社の宮司は代々高麗王若光の子孫である高麗氏が務めています。
高句麗は668年に唐に滅ぼされたため、高句麗の人達は日本に避難をしてきました。その人達が朝廷の命令で武蔵国に集められ、その地域が高麗郡と名づけられました。
高麗郡に済む人達のリーダーには高句麗の王族であった高麗王若光がおり、高麗王若光が亡くなると霊廟が建てられそれが高麗神社となりました。
高麗神社の宮司は代々高麗王若光の子孫である高麗氏が務めています。
宇治土公氏
宇治土公氏は猿田彦命(サルタヒコノミコト)の子孫である大田命を祖としている豪族です。
宇治土公氏は代々邸宅の敷地内にあった屋敷神として猿田彦命を祭っていましたが、明治になり屋敷神を改めて猿田彦神社としました。
宇治土公氏は代々邸宅の敷地内にあった屋敷神として猿田彦命を祭っていましたが、明治になり屋敷神を改めて猿田彦神社としました。
荒木田氏
荒木田氏は天見通命を祖とする豪族で、成務天皇のとき荒木田姓を下賜されたといわれています。
社家でもあり明治時代まで代々伊勢皇大神宮(伊勢神宮内宮)の祠官を世襲していました。
社家でもあり明治時代まで代々伊勢皇大神宮(伊勢神宮内宮)の祠官を世襲していました。
度会氏
度会氏は天牟羅雲命を祖とする豪族で、社家でもあり明治時代まで代々伊勢豊受大神宮(伊勢神宮外宮)の祠官を世襲していました。
壬生吉志
壬生吉志は埼玉県北部に位置した男衾郡を支配していた豪族で、渡来系の氏族と考えられています。
近くを流れる荒川の脇には鹿島古墳群があり、一連の古墳は生吉志氏に関連したものという説が有ります。
近くを流れる荒川の脇には鹿島古墳群があり、一連の古墳は生吉志氏に関連したものという説が有ります。
関連ページ
▲先頭へ▲